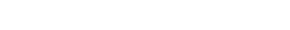本物を子どもたちに――0.001グラム単位の精度を追求し優勝トロフィーを生んだ岩井工業の職人魂
岩井工業 株式会社 代表取締役 小山幹雄 1978年創業の金属部品試作メーカー人材や設備への投資を惜しまず技術革新に挑戦し、自動車業界の厳しい品質基準に対応してきました。昭和の名工作機と最新設備を融合させ、自社一貫生産体制で高品質なものづくりを実現。会社情報はこちら ------ 少年サッカー大会「KAIHAN CUP」。未来ある子どもたちが熱戦を繰り広げるこの舞台に、ひときわ輝きを放つ存在がある。それは優勝チームに授与されるトロフィーだ。本物のワールドカップの優勝トロフィーと同じ6.175kgのトロフィー。一見すればただのトロフィー。しかし、その背後には、0.001グラム単位の精度を追い求めた設計と、熟練の技を尽くした職人たちの挑戦が隠されている。製作を担ったのは、自動車部品などの金属加工を手がける岩井工業さん。今回はその製作秘話を小山社長とプロジェクトリーダーの瀬賀さんにうかがった。 ※このインタビューは2025年8月27日に実施しました。 0.001グラムの攻防戦 最初に課された条件は「トロフィーの総重量6.175kgで仕上げること」。その数値は、0.001グラム単位という異例の精度で指定された。「重く作って削るのは難しい。だから、まず軽めに設計して最後に微調整するんです」と小山社長は語る。部品一つひとつを削り出すたびに重さを測定し、組み立て後・塗装後にどれだけ増えるかを常に予測する。ネジ1本、塗料の厚みまで想定しながらの製作は、まるで時計職人のような緻密さだった。最後の段階では内側をわずかに削り、台座に据えた瞬間にぴたりと6.175kgに収める。これは「偶然ではなく、積み重ねた技術が生んだ必然」だった。 サッカーボールを金属で表現する挑戦 トロフィーの象徴であるボール部分は、ステンレスのパーツを一枚ずつ組み合わせて作られる。ここに大きな見どころがある。「溶接の跡を消しすぎれば、ただの丸い球になってしまう。あえて“残す”ことで、本物のサッカーボールの模様が浮かび上がるんです。」熱の加え具合、スピード、磨きの力加減、すべてが職人の経験に委ねられる。息を止め、一瞬で溶接を決める。熟練者の“勘”がなければ、美しい模様は決して出せない。完成品を前にすれば、誰もが「まるで本物のボールだ」と錯覚するほど。だがその裏には、数ミリ単位の試作と失敗が積み重ねられていた。 削り出しの技と、協力工場の知恵 胴体部分は、ステンレスの塊をコンピュータ制御の機械で削り出していく。だが、同じ設計データでも全く同一のものはできない。微細な傷や想定外の掘り残しに何度も直面した。とはいえ、そこは熟練の技術者たちだ。結果として試作品は2つ製作され、そのうち一つがトロフィーとして完成したという。さらに、塗装やメッキには特有の課題があった。ステンレスは塗料がのりにくい素材であり、通常の方法では美しい発色が得られない。ここで立ち上がったのが協力工場の職人たちだった。「“子どもたちに本物を渡したい”という思いに皆が共感してくれて。毎日のように塗装屋さん、メッキ屋さんに通って、何度もサンプルを出して試行錯誤しました。」と、プロジェクトリーダーの瀬賀さんが語ってくれた。岩井工業の職員は、休みも返上して工場を往復。職人同士の知恵と情熱のリレーが、唯一無二の輝きを生み出した。 苦闘のディテールーーー台座とケース 今回の製作で最も難関となったのは、じつは台座部分と特注ケースだった。 台座には円錐状の先細り部分に文字プレートを貼るという指示があった。斜めに文字を配置すれば歪んで見えるため、何度も位置を変えてやり直す必要があった。加えて、台座と同じ色合いを持たせるために新しいメッキ技術を導入。時間ぎりぎりまで調整が続けられた。さらに、トロフィーを収納する専用ケースも簡単ではなかった。 設計図だけでは製作できず、完成品そのものを関西のケースメーカーに送り、現物合わせで調整。輸送中の破損や紛失のリスクを抱えながらも、子どもたちに完璧な形で届けるために決断を下した。 製作期間は2か月。「納期は決勝戦の日。絶対に間に合わせなければならない。」その覚悟が、多くの大人たちを突き動かした “本物”が子どもたちの心に残すもの KAIHAN CUPが一番大切にしていたのは、「子どもたちに本物を手渡すこと」だった。小山社長もその想いに共感してここまで本気で動いた。「軽くて壊れやすいおもちゃのようなトロフィーでは、自己肯定感は育ちません。本物を手にして、その重さを感じることで、“自分たちは大切に扱われている”と実感してほしいんです。」トロフィーの重量感は、努力と勝利の証として子どもたちの記憶に刻まれる。さらに、製作に携わった職人たちの思いが重なり、その価値は一層深まる。 安価で使い捨ての製品があふれる時代だからこそ、「本物を大切にする感覚」を伝えたい。その信念が岩井工業をはじめ多くの大人たちを突き動かした。 未来へのバトン 完成したトロフィーは、単なる大会の副賞ではない。大人たちの情熱と技術の結晶であり、子どもたちに託された未来へのバトンだ。...